この記事では、「ゲーム業界に入って後悔したこと」について解説します。
結論から言うと、以下の10選です。
ゲーム業界に憧れて就職したものの、「思っていたのと違う…」「もう辞めたいかも」と感じる人は意外と多いです。
「好きなことを仕事にしたい」という思いで飛び込んだはずが、理想とのギャップに後悔するケースも少なくありません。
この記事では、実際にゲーム業界で「後悔した」と感じた人たちの声をもとに、よくある理由を10個に整理。
あわせて、これからゲーム業界を目指す方に向けて、後悔しないための企業選びのコツや、働き方のヒントも紹介していきます。
ゲーム業界に入って後悔したこと10選

では、ゲーム業界に入って後悔したことを解説していきます。
前提として、全ての企業が当てはまるわけではありません。
全て該当するブラック企業もあれば、全く該当しないホワイト企業もありますからね!
後悔したこと①:長時間労働と納期のプレッシャー
ゲーム業界に入って後悔したこと1こめは、「長時間労働と納期のプレッシャー」です。
特にリリース前や大型アップデート直前などは、深夜残業や休日出勤が当たり前になりがちで、メンタル病む人はそこそこいます。
ゲーム業界の2024年時点の平均週労働時間は、通常期で約44.7時間、繁忙期は52.6時間と言われています(出典:CESA調査)。
これを残業時間に換算すると──
| 残業時間 | |
|---|---|
| 通常期 | 約18.8時間/月 |
| 繁忙期 | 約50.4時間/月 |
つまり、「普段はそこまでじゃないけど、リリース前などの繁忙期は長時間労働」です。
年単位で見ると、平均残業時間は24〜26時間ほどとされており、昔に比べてかなり改善されています。
ただし、これはあくまで“平均”です。
現場によっては、長時間労働が常態化している会社もあります。
たとえば──
- 上司のこだわりが強すぎる
- 独身者が多くて生活のリズムが合わない
- 売り上げがきつい
- 完全受託開発で経営が怪しい
上記のような環境だと、働き方への配慮が薄くなり、結果的に残業が増えるケースもあります。
また、ゲーム業界は、「納期に厳しい」です。
自分のタスクが遅れると、次の工程にしわ寄せがいくため、チーム全体に影響が出ます。
ゲーム開発は一人で完結する仕事ではなく、複数人で進める分業体制ですからね。
夢を追って入った業界なのに、体力的にも精神的にもキツい…と感じ、後悔する人は実際に多いです。
後悔したこと②:初任給が低く、昇給もゆるやか
ゲーム業界に入って後悔したこと2こめは、「初任給が低く、昇給もゆるやか」です。
多くの企業では、未経験者や新卒のスタート年収が240〜300万円台に設定されており、生活に余裕があるとは言えません。
さらに、業界全体で賞与が少なかったり、年俸制や見込み残業込みの給与体系を採用している企業も多いため、「実働に見合わない」と感じるケースも多いです。
以下は、ゲームクリエーターの平均年収です。
| 3年以下 | 3~6年 | 6~9年 | 12~15年 | |
|---|---|---|---|---|
| 平均年収 | 407.8万円 | 497.9万円 | 572.3万円 | 644万円 |
ゲームクリエーターの平均年収は「560~580万円」ほどで、日本人全体の平均年収(約461万円)より少し高めです。(引用:jogtag)
ただし、この水準に届くには6〜9年ほどの経験や実績が必要。
大卒なら28〜31歳くらいが目安です。
| 平均年収 | |
|---|---|
| CGデザイナー | 478万6,000円 |
| イラストレーター | 486万9,000円 |
| プロジェクトマネージャー | 733万6,000円 |
| プログラマー | 523万円 |
もちろん、会社の規模や役職、スキルによって年収はかなり変わります。
昇給についても、評価基準が曖昧な職場では、給与アップまでに長い時間がかかることも。
企業規模によっては、年1回の昇給が5,000円のところもありますからね。
「好きだけではやっていけない」と感じる瞬間のひとつです。
正直なところ、ゲーム業界で年収をあげるには、転職が手っ取り早いです。
後悔したこと③:やりたい仕事に関われない
ゲーム業界に入って後悔したこと3こめは、「やりたい仕事に関われない」です。
ゲーム業界に入ったものの、「思い描いていた仕事ができない」と後悔する人は少なくありません。
たとえば、プランナー志望だったのに仕様書の入力やExcel管理ばかり、デザイナーとして入社したのにバナー制作や既存素材の修正ばかり……というのはよくある話。
ゲーム開発はチームで動くため、自分の希望よりも“現場の人手不足”が優先されがちです。
また、企画やオリジナル開発に関わりたくて入社しても、IP作品の運営や受託業務がメインで、想像と違ったという声も。
特に未経験や若手のうちは、希望を通すのが難しいんですよ。
なので、入社前に配属や業務内容をしっかり確認しておかないと、ギャップに苦しむことになります。
夢と現実の差に後悔しないよう注意が必要です。
後悔したこと④:尖った人が多く、人間関係に疲れる
ゲーム業界に入って後悔したこと4こめは、「尖った人が多く、人間関係に疲れる」です。
クリエイティブな仕事が多いため、個性やこだわりの強い人が多く、コミュニケーションが難しい場合があります。
中には、自分の考えを押しつけたり、無神経な言動をとる人もいて、やりとりに神経をすり減らすことも。
他業種と比べてオタク気質の人が多く、「ちょっとねちっこいな…」と感じる瞬間があるのも事実です。
たまに、ここはサークルかな?って思うことも―――。
もちろん、優しくて協力的な人もたくさんいますが、人間関係にストレスを感じて離職するケースも珍しくありません。
後悔したこと⑤:労働環境がプロジェクト次第
ゲーム業界に入って後悔したこと5こめは、「労働環境がプロジェクト次第で大きく変わる」です。
同じ会社内でも、どのプロジェクトに配属されるかで働き方・忙しさ・人間関係がまったく違うんですよね。
たとえば、前のチームでは定時退社が当たり前だったのに、異動先では毎日深夜まで残業…なんてことも普通にあります。
スケジュール感、上長の方針、チームメンバーとの相性など、さまざまな要因が絡むため、安定しにくいのが現実です。
「会社自体はホワイトだけど、今のプロジェクトが地獄」というのもあります。
実際わたしも、「他チームは定時で帰ってるのに、自分のとこだけ炎上して4カ月ずっと残業続き」という状況を経験しました。
特に未経験や若手の場合は、自分の希望とまったく違うチームに配属されることも多く、モヤモヤすることも多いと思います。
後悔したこと⑥:ブラック体質な企業が一定数残っている
ゲーム業界に入って後悔したこと6こめは、「ブラック体質な企業が一定数残っている」です。
働き方改革が進んだとはいえ、ゲーム業界には今なお古い体質のまま運営されている企業が存在します。
「見込み残業込みの年俸制」「休日出勤が当たり前」「パワハラ・セクハラ体質が放置」など、環境が整っていない会社もちらほら。
特に中小規模や、オーナー色の強いパブリッシャー企業に多く見られる傾向があります。
表向きはオシャレで楽しそうなオフィスでも、実態は“好き”を搾取する構造になっているケースも…。
だからこそ、応募前に口コミサイトや転職エージェントを活用して、企業の実態をしっかり確認することが大切です。
後悔したこと⑦:評価の基準が不明確
ゲーム業界に入って後悔したこと7こめは、「評価の基準が不明確でモヤモヤする」です。
ゲーム開発はチームで行うため、個人の成果が見えにくく、評価があいまいになりがちです。
たとえ同じような貢献をしていても、「上司に気に入られている人の方が評価される」といった場面も少なくありません。
実際に、実力よりも“上司との距離感”で昇給やポジションが決まるようなケースもありますよ。
「実力ないのに偉そうにしていてめんどくさい人」とか―――。
実力主義とうたってはいても、裏では“忖度”が評価に影響する現場もあるのが正直なところです。
後悔したこと⑧:ゲームを純粋に楽しめなくなる
ゲーム業界に入って後悔したこと8こめは、「ゲームを純粋に楽しめなくなる」です。
元々「ゲームが大好きだから仕事にしたい」と思って入った人ほど、現場に入ってから理想とのギャップを感じることが多いです。
というのも、開発に携わると「プレイヤー」ではなく「作り手」の視点になります。
ゲームをプレイしていても「仕様の確認」「バグ探し」「競合チェック」といった、分析目線が染みついてしまうんですよね。
気がつけば義務感だけで触れている状態に…。
後悔したこと⑨:納得できない仕様でも従わなければならない
ゲーム業界に入って後悔したこと9こめは、「納得できない仕様でも従わなければならない場面が多い」です。
ゲーム開発は、理想と現実のギャップに悩まされがちです。
特に商業的な視点が強い現場では、「面白いか」よりも「他社で成功した型に倣う」ことが優先されがちです。
「これ…正直あまり面白くないよな」と思う仕様でも、上からの指示があれば従うしかない。
現場レベルで「これ面白いよね」と盛り上がっていた企画も、経営陣のひと声で「あの人気タイトルっぽくして」と方向転換が入り、全修正―――なんてことも全然ある。
結果、「これじゃあただの業務じゃん…」と感じてしまい、ゲームに対する熱意がしぼんでしまう人も多いです。
特に若手や下請けの立場では、自分の意見を反映させることが難しく、モヤモヤを抱えながら仕事を続けるケースも少なくありません。
後悔したこと⑩:家庭を持つ人への理解が乏しいこと
ゲーム業界に入って後悔したこと10こめは、「家庭を持つ人への理解が乏しい」です。
業界全体としては20〜30代の独身者が多いため、育児や家族との時間に対する配慮が欠けがちです。
※「家庭持ちや子持ちが偉いとか優先すべき」という意味ではなく、ハラスメントに近いノンデリ発言が多いという意味。
無礼な発言があったりするから、「子どもが熱を出して…」と伝えるのも気まずいです。
もちろん会社によって違いはあるものの、「家庭より仕事優先」といった価値観が色濃く残っている現場も少なくありません。
家族との時間を大切にしたい人にとっては、疎外感を覚えたり、居心地の悪さを感じてしまうこともあります。
以上が、ゲーム業界に入って後悔したこと10選になります。
繰り返しになりますが、全ての企業に当てはまるわけではありません。
わたし自身の体験したことや、周囲の方からの意見を参考にしています。
ゲーム業界が気になるけれど後悔したくないという人は、エージェントなどを利用して慎重に企業選びをしましょう。
①UZUZ 新卒
大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!
②キャリセン就活エージェント
利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!
【体験談】わたし自身ゲーム業界に入って後悔したのか?

結論から言うと、私はゲーム業界に入って後悔していません。
むしろ「入ってよかった」と心から思っています。
ゲーム開発は本当に楽しく、特にチームで少しずつ形にしていく感覚は、他では味わえないワクワクがあります。
テストフェーズで完成に近づいていく瞬間は、感動ものです。
リリース後もユーザーさんの反応が見れて、めちゃくちゃ感動しますよ。
最新技術に触れるチャンスも多く、自社開発に関わっていた時は、ポートフォリオや実績もしっかり積むことができました。
ただ、ひとつだけ後悔していることがあります。
それは「最初の会社選びを間違えたこと」です。
ゲーム業界で最初に入った会社は、いわゆるブラック企業。
パワハラが横行し、慢性的な長時間労働で体も心もすり減りました。
デザイナーは自分を含めて全員が辞め、残ったのは疲弊した現場だけ。
私自身も限界がきて、パニック障害のような症状が出てしまい、2年半で退職。
その後、ホワイトなゲーム会社に転職したところ、定時で帰れるし、上司も尊敬できる人で、仕事が本当に楽しかったです。
だからこそ痛感しています。
「ゲーム業界は、企業選びがすべて」です。
私は最初、エージェントも口コミサイトも使わず、自力で探してしまったのですが、今思えば非効率!
第三者の意見を取り入れて、最初から“ちゃんとした会社”を選んでいれば、体調を崩すこともなく、もっとゲーム開発に集中できたと思います。
これからゲーム業界を目指す方には、遠回りせず、最初から信頼できる方法で企業選びをしてほしいです。
ゲーム業界で後悔しない企業選びのポイント5選

つぎに、ゲーム業界で後悔しない企業選びのポイントを解説していきます。
①:口コミサイトを徹底的に確認する
企業の口コミサイト(転職会議・openwork)を徹底的に確認しましょう。
実際筆者も数回使用しました。
チェックすべきポイントは、以下のような項目です。
- 残業時間
- 有給の取りやすさ
- 育成制度
- 離職率
また「権利者の申し立てにより削除されました」という表記が多い企業には注意しましょう。
このメッセージは、会社側が口コミの削除申請をした証拠です。
削除される理由はさまざまですが、よくあるパターンとしては、
- ブラックな環境の暴露
- 会社と揉めた
- ただの悪質なもの
…といった背景があります。
もちろんすべてが事実とは限りませんが、「削除が多い=何か隠したい事情がある」と考えるのが自然です。
※転職会議の口コミは『無難な内容』or『暴露悪口』の2極化しています。
②:開発実績を事前に調べる
就職先として検討している企業が、どんなゲームを開発しているのかは必ず確認しましょう。
開発実績や得意とするジャンルを知ることで、自分のやりたいこととズレがないかを確認できます。
たとえば「コンシューマーゲームを作りたい」と思って入社したのに、実はソシャゲの受託案件ばかりだった…となると、入社後にミスマッチを感じる原因になります。
また、「自社開発か受託開発か」によって、関われる業務の幅や裁量も大きく変わります。
適当な企業を選んでミスマッチが起きれば、期間損失がハンパないですからね。
③:面接での空気感・質問対応で判断する
面接官の態度からブラック企業の可能性を探ることができます。
たとえば、こんな態度が見られたら要注意。
- 何もリアクションをとらない。
- むすっとした態度。
- 横柄な態度。
- 急にキレる。
- 異様なほど上から目線で話す。
こういう面接官がいる会社は、入社後もそのノリで接してくる可能性が高いです。
つまり、働く環境としてはかなりしんどい。
実際、筆者の体験では「面接中に社長がタバコを吸い出した」なんて会社もありました。
案の定ブラックでしたけどね…。
また、現場の社員が同席するパターンでは、その人の表情にも注目です。
目が死んでたり、明らかに疲弊している様子だったりしたら、職場環境がキツすぎるサインかもしれません。
面接のわずかな空気感からでもヒントは拾えます。
「ちょっと違和感あるな」と感じたら、その直感を大事にしましょう。
④:未経験・第二新卒可の求人は要注意
若手向けの求人って、ブラック率が高めです。
特に「未経験OK」「第二新卒歓迎」といった募集は注意が必要。
さらに、年中募集している企業は退職率が高い可能性があるので警戒しておきましょう。
なぜなら、若手がどんどん辞めていくため、「とにかく人手が欲しい!」という状態に陥ってる会社もあるんです。
ぶっちゃけ「未経験歓迎」「第二新卒OK」は、”誰でもいいから来てほしい”という意味になります。
中途採用でなかなか応募が来ないから、とりあえず間口を広げて人を集めているという感じですね。
なので、勢いだけでガンガン応募するのはNG。
ちゃんと見極めましょう。
とはいえ、全部がブラックというわけでもありません。
実際、筆者が昔働いていたホワイト企業でも、第二新卒歓迎の求人を出していました。
また、職歴が少しでもあれば、「未経験OK」ではなく、中途採用枠に挑戦するのもアリです。
条件を100%満たしていなくても、6〜7割くらい合っていれば採用されることもありますし、募集要項はあくまで目安。
迷ったら応募してみるのもアリですよ。
⑤:ブラックを排除したエージェントを活用する
ゲーム会社を目指すなら、転職エージェントの登録は必須です。
理由はシンプルで、ゲーム業界に詳しい情報やアドバイスが手に入るから。
これだけで転職の成功率が大きく変わります。
ゲーム業界の転職者を多く担当するため、”人員の流出入”や”ブラック企業の情報”に詳しいですよね。
紹介する企業に基準を設けて、ブラック企業を排除しているエージェントもあります。
ただし、エージェントの質は担当者によってピンキリ。
「やる気ないな〜」って人や、無理に応募を勧めてくる人に当たることもしばしば。
だからこそ、おすすめは「複数の転職エージェントに登録すること」です。
まず、大手・特化型・ブラック排除に登録して、様子をみましょう。
自分に合っているか、使いながら判断すればOKです。
また、エージェントには他社も使ってることを伝えるのがコツ。
エージェントは、就職が決まって初めて報酬が発生する仕組みなので、「紹介が微妙なら他に頼るよ」と遠回しに伝えるだけで、対応が変わることもあります。
ただし、スキルや経歴に自信がない場合は、紹介が止まることもあるので注意!
本当に親身になって話を聞いてくれる担当に出会えるまで、複数登録して相性チェックしましょう。
「やたら強引だな」「なんか信用できないな」と感じる担当は、すぐに切り替えてOKです!
①UZUZ 新卒
大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!
②キャリセン就活エージェント
利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!
ゲーム業界で後悔しない働き方4選
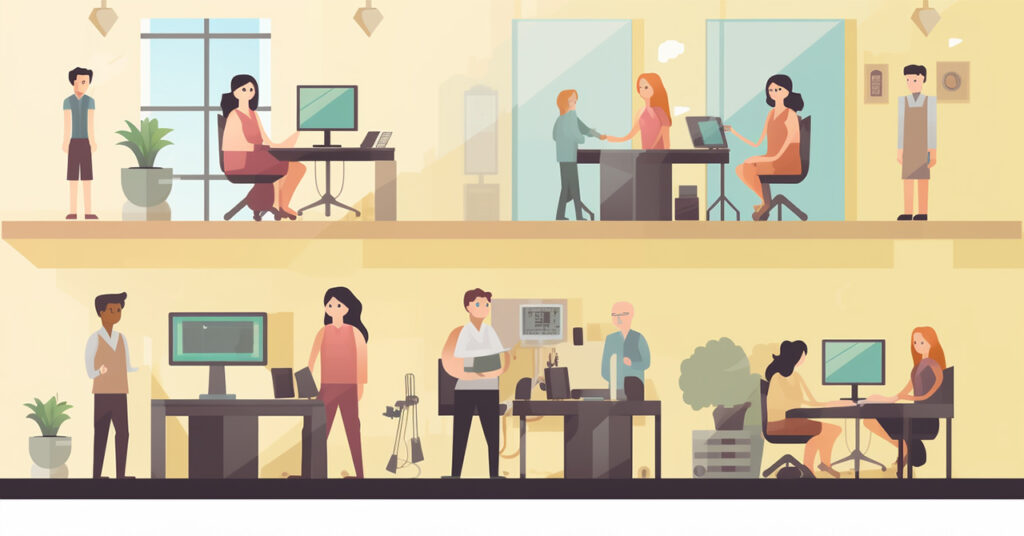
つぎに、ゲーム業界で後悔しない働き方を解説していきます。
①:自社開発企業を選ぶ
自分のアイデアを形にしたい、オリジナルのゲームを作りたいという人には、自社開発企業がおすすめです。
自社開発では、企画段階から開発・運営まで社内で完結するため、自分の意見が反映されやすく、やりがいも大きいです。
もちろん自社開発企業でもハードな場面も多い。
それでも、チームでアイデアを出し合い、ゼロから作り上げていく体験は、他では得られない魅力です。
②:他業種でも使えるスキルを意識する
ゲーム業界で働くうえで重要なのは、「他業種でも通用するスキル」を意識して身につけることです。
というのも、ゲーム業界はプロジェクト単位で動くことが多く、転職や離職が当たり前の業界でもあります。
そのため、いざというときに備えて“つぶしが利くスキル”を持っておくと安心です。
たとえば、エンジニアであれば汎用性の高いプログラミング言語やインフラの知識、デザイナーであればUI/UX設計や動画制作のスキルなどは、IT業界でも需要があります。
「今の会社を辞めたらどうなる?」という視点でキャリアを考えておくと、いざという時に後悔しません。
ゲーム業界特化しすぎると、将来の選択肢が減りますからね。
③:派遣・契約社員も“試す場”として活用する
ゲーム業界は人気が高く、正社員の求人は倍率も高め。
特に未経験者の場合、いきなり正社員として採用されるのはそう簡単ではありません。
だからこそ、「派遣」や「契約社員」といった雇用形態を“お試し”として活用するのは、十分にアリ。
実際に現場で働くことで、自分にその仕事が合っているかどうか、どんなスキルが求められるのかを体感できます。
また、実力を認められて正社員登用されるケースも少なくありません。
ただし、この方法は、誰しもにおすすめできるわけではありません。
正社員が確定しているわけでもないので。
とはいえ、「まずは現場を経験したい」「ゲーム業界の空気を知りたい」という人にとっては、良いステップになります。
④:副業も進めておく
デザイナーやエンジニアなど専門スキルを持つ職種は、副業との相性が抜群です。
本業とは異なるジャンルの仕事にチャレンジすることで、視野が広がり、新たなスキルや発見を得られることも多いでしょう。
また、万が一ゲーム業界を離れたくなったときでも、副業の実績があれば他業種への転職がスムーズになるケースもあります。
収入源が分散されていると、精神的な余裕にもつながります。
ハードな環境であるゲーム業界だからこそ、いざという時の“保険”として、副業を取り入れておくのは非常に有効なんですよ。
優良ゲーム企業を狙うならエージェントがおすすめ
行動するだけならノーリスク
ゲーム業界に少しでも興味があるなら、まずは一歩踏み出してみることをおすすめします。
「やってみたい」と思っているのに行動しないのは、機会損失です。
迷っているなら、まずは転職エージェントや転職サイトに登録して情報を集めることから始めてみましょう。
登録って、正直ちょっと面倒くさいですよね。
でも、面倒に感じるその瞬間こそ、動き出すチャンスです。
転職エージェントは、ゲーム会社とのパイプラインがあります。
例えば、エージェントが企業の採用担当との関係性が深いケースもあるんですよ。
「どんな受け答えが好印象を与えるか」や「ブラック企業の見分け方」など、現場のリアルな情報を教えてもらえるのが強みです。
「まずは話だけでも聞いてみようかな」くらいの気持ちでOKです。
もしエージェントは気が重いな…と感じる方は、転職サイトに登録して気になる求人をチェックするだけでも立派な第一歩です。
スキマ時間に求人を眺めたり、気になる案件をストックしたり、自分に合ったチャンスを見逃さない準備ができますよ。
①UZUZ 新卒
大手を含む様々な優良企業を紹介してくれる転職支援サービス。ブラック企業を徹底排除。完全オーダーメイドで面接対策!
②キャリセン就活エージェント
利用後の内定獲得5.4倍の新卒向け就活支援サービス。これまでに6万人以上の学生が利用しています。Googleクチコミ★4.8。年間取引企業1,000社以上!
本記事のまとめ|ゲーム業界に入って後悔するかもしれないが、ゲーム開発は非常に楽しい!
- ゲーム業界は、企業選びさえ間違えなければ後悔しない。
- 近年の労働環境は、改善の道をたどっている。
- 給与は、日本人の平均年収より高い傾向にある。
- 年収を上げるには転職することが手っ取り早い。
- 家庭持ちには、厳しい環境。
- ゲーム開発は、非常に楽しい!
- ゲーム業界に長くいるには、企業選びが重要!
ゲームが好きなら、ゲーム業界は本当におすすめのフィールドです。
開発に関わるのは大変なこともありますが、それ以上にワクワクと達成感に満ちた仕事ですよ!
「自分が携わったゲームが世に出る」って、やっぱり特別な体験ですよ。
未経験の場合は「どこでもいいから!」くらいの勢いで、入社される方もたくさんいるでしょう。
最悪、それでも大丈夫です。
まずは現場に入って経験を積み、合わないと感じたら転職して軌道修正すれば大丈夫。
ただし、健康だけは本当に大切にしてください!
ゲーム業界はどうしても体力勝負な面もあるので、若いうちにチャレンジしておくのがベスト。
